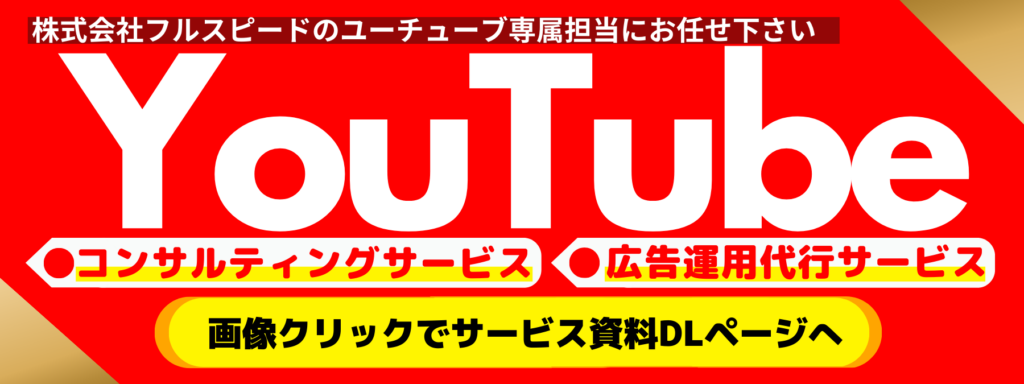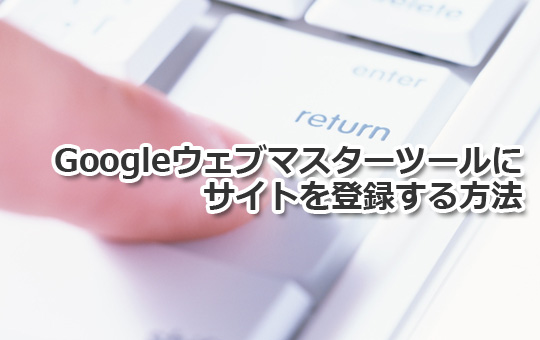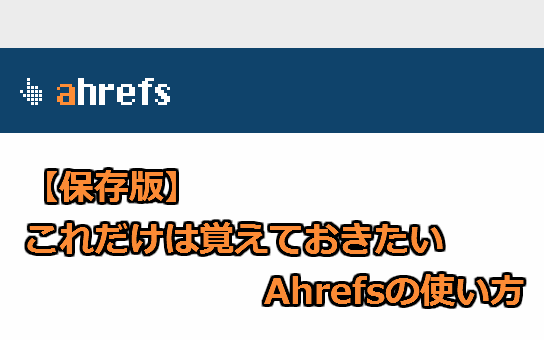ウェブマスターツールにサイトを登録する方法
【業界別】2024年企業のYouTubeチャンネル活用事例まとめ
- Youtube
公開日:2020年09月01日
最終更新日:2024年08月30日

●美容・医療業界のYouTubeチャンネル活用事例が分かる
●飲食店・コンビニ業界のYouTubeチャンネル活用事例が分かる
●アパレル・雑貨業界のYouTubeチャンネル活用事例が分かる
●マスコミ業界のYouTubeチャンネル活用事例が分かる
●金融・保険業界のYouTubeチャンネル活用事例が分かる
●BtoB企業のYouTubeチャンネル活用事例が分かる
●その他のYouTubeチャンネル活用事例が分かる
(※2024年8月30日現在)
当記事では「業界別の企業YouTubeチャンネル活動事例まとめ」と題して、8種類(食品業界/美容・医療業界/飲食店・コンビニ業界/アパレル・雑貨業界/マスコミ業界/金融・保険業界/BtoB企業/その他)の事例についてご紹介いたします。
YouTubeを始めたばかりで運用方法を模索している、運用してはいるがあまり効果が上がらない、という企業さんはぜひ参考にしてみてください。
(※過去の弊社調査では20~40代の約47%のユーザーがYouTubeの動画を見た後に購買や来店などの行動を起こした経験があると答えています)
↓「企業のYouTubeチャンネル運用ガイドブック」を無料で受け取る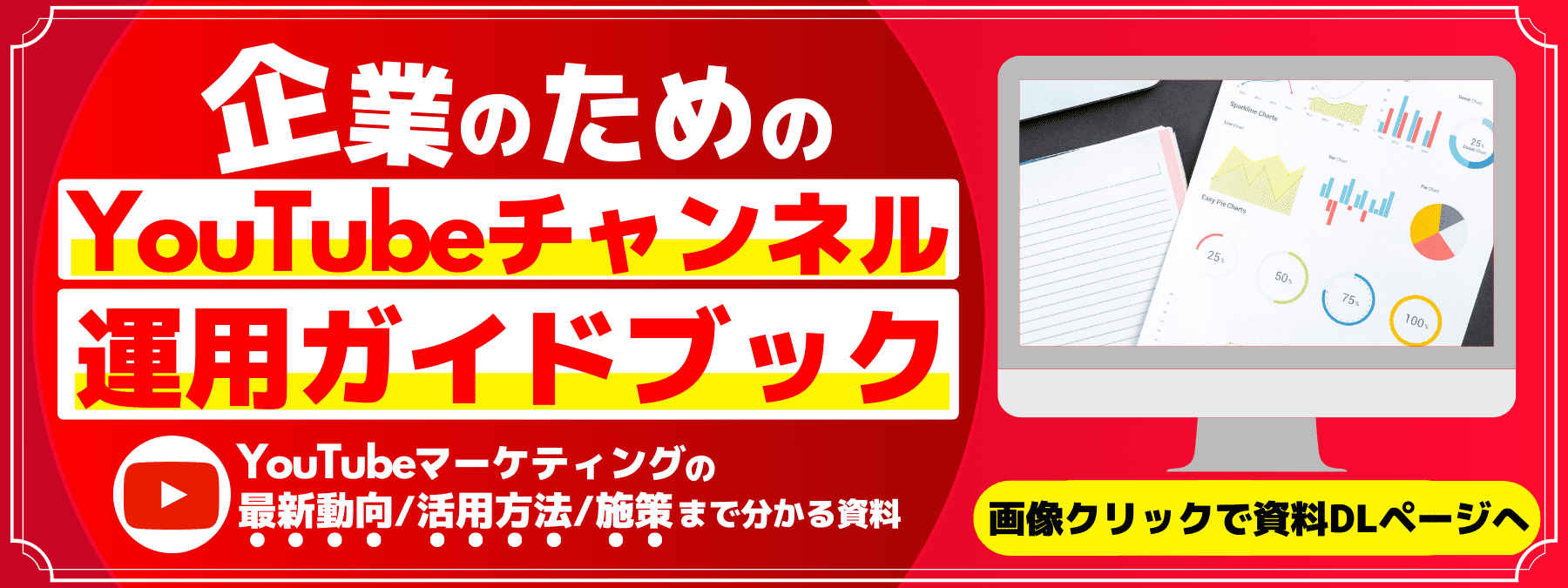
目次
食品業界のYouTubeチャンネル活用事例まとめ
食品業界のYouTubeチャンネル10選
| 企業名 | チャンネル | 登録者数 | 投稿数 | 視聴回数 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒグループホールディングス株式会社 | アサヒグループ公式チャンネル | 14.5万人 | 680本 | 211,523,106回 | 2011/09/20 |
| キリンビバレッジ株式会社 | キリンビバレッジ | 9.98万人 | 156本 | 82,122,487回 | 2014/02/28 |
| サントリーホールディングス株式会社 | サントリー公式チャンネル(SUNTORY) | 36.8万人 | 1,819本 | 509,457,189回 | 2013/10/30 |
| 株式会社 明治 | 株式会社 明治 | 8.21万人 | 568本 | 108,656,850回 | 2011/06/13 |
| 日本ハム株式会社 | NipponhamGroup | 6830人 | 139本 | 25,054,543回 | 2011/12/26 |
| 味の素株式会社 | 味の素KK公式チャンネル(AJINOMOTO OFFICIAL) | 19.7万人 | 304本 | 825,519,007回 | 2006/01/19 |
| 日本コカ・コーラ株式会社 | コカ・コーラ | 11.1万人 | 311本 | 76,659,744回 | 2011/03/30 |
| 伊藤ハム株式会社 | 伊藤ハム公式チャンネル | 7880人 | 280本 | 36,521,745回 | 2012/02/22 |
| 株式会社伊藤園 | 伊藤園公式チャンネル | 1.62万人 | 451本 | 20,271,988回 | 2014/05/23 |
| 雪印メグミルク株式会社 | 雪印メグミルク公式チャンネル | 1.38万人 | 244本 | 70,457,351回 | 2017/02/20 |
(2024年8月29日現在)
食品業界のYouTube運用の特徴
食品業界は、テレビでCMを積極的に発信していることから、YouTubeでもテレビCMや関連したWeb動画を投稿していることが多いです。
一企業でも多数の商品を発売しているためCMのバリエーションが豊富なので、コンテンツが枯渇してしまうことがなかったり、様々な出演者のファンを取り込めたりすることが特徴だと言えます。
テレビCM等での露出が多い上、ユーザーの生活に欠かせない商品のため認知度が高いということもあってか、登録者数はどの企業も比較的多く、20万人を超えている企業もみられます。
テレビCM以外には、自社商品を使ったレシピ動画などが投稿されている傾向にありました。
注目チャンネル①アサヒグループ公式チャンネル
ビールを中心とした飲料を製造・販売するアサヒグループでは、タレントを起用したプロモーション動画に加え、商品自体とはあまり関係のないレシピ動画なども公開しています。
「おつまみ」としてレシピを紹介することでビールと親和性が高く、自社商品と動画を一緒に楽しんでもらえる仕掛けとなっています。
注目チャンネル②株式会社 明治
明治では、自社商品を使ったレシピ紹介やアスリートへのインタビュー動画などを公開しています。新型コロナウイルスにより外出が自粛されていた2020年4月に投稿されたヨーグルトアートのシリーズは、自宅でみんなで楽しめるので自粛中の「おうち時間」と相性が良いコンテンツとなっています。
美容・医療業界のYouTubeチャンネル活用事例まとめ
美容・医療業界のYouTubeチャンネル10選
| 企業名 | チャンネル | 登録者数 | 投稿数 | 視聴回数 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社資生堂 | 資生堂 Shiseido Co., Ltd. | 10.6万人 | 1,763本 | 147,737,892回 | 2012/03/28 |
| 株式会社コーセー | KOSECOSMEPORT | 2.03万人 | 98本 | 19,085,510回 | 2015/03/25 |
| 株式会社ミルボン | milbon ミルボン | 9760人 | 348本 | 5,511,195回 | 2011/06/17 |
| P&Gプレステージ合同会社 | SK-II Japan | 5.7万人 | 45本 | 170,016,511回 | 2012/04/09 |
| 株式会社ファンケル | FANCLjapan | 1.16万人 | 418本 | 168,863,701回 | 2012/04/03 |
| 花王株式会社 | KaoJapan | 9.39万人 | 1,283本 | 355,673,278回 | 2011/03/31 |
| 中外製薬株式会社 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 1.22万人 | 111本 | 30,028,654回 | 2014/11/23 |
| 第一三共ヘルスケア株式会社 | 公式チャンネル第一三共ヘルスケア | 6420人 | 74本 | 56,551,904回 | 2014/09/26 |
| 株式会社ヴィエリス | KIREIMO TV | 4410人 | 181本 | 6,446,022回 | 2016/06/20 |
| 株式会社AB&Company | アグヘアーCh | 4450人 | 155本 | 2,432,472回 | 2019/05/31 |
(2024年8月29日現在)
美容・医療業界のYouTube運用の特徴
美容業界では、テレビCMや商品紹介動画、使い方に関する動画が多く投稿されています。動画にはモデルや女優を起用し、明るく美しい雰囲気の投稿で統一されている傾向がみられます。
特に商品の使い方紹介は、企業が自ら発信しているためユーザーからの信頼性が高くなると考えられます。
注目チャンネル①FANCLjapan
FANCLでは、商品紹介だけでなくトレーニング動画やレシピ紹介なども投稿しており、「美」という大きなテーマでコンテンツを制作していることが分かります。
誰もが関心を持ちやすいコンテンツによってユーザーを取り込み、ファン作りをしています。
注目チャンネル②アグヘアーCh
全国に店舗を持つ美容室アグヘアーでは、ヘアケアやヘアアレンジの方法、自宅でもできる簡単なヘアカット方法まで、髪に関する知識を惜しみなく発信しています。
登録者数は約4200人(2024年1月時点)ですが中には60万回近く視聴されている動画もあり、登録者数が少なくてもコンテンツ次第で多くの人の目に触れ、企業の知名度を上げられると言えます。
飲食店・コンビニ業界のYouTubeチャンネル活用事例まとめ
飲食店・コンビニ業界のYouTubeチャンネル10選
| 企業名 | チャンネル | 登録者数 | 投稿数 | 視聴回数 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本マクドナルド株式会社 | マクドナルド公式(McDonald’s) | 22.4万人 | 87本 | 27,023,069回 | 2009/07/06 |
| スターバックスコーヒージャパン株式会社 | スターバックス 公式 | 2.1万人 | 133本 | 2,621,889回 | 2011/09/01 |
| 日本KFCホールディングス株式会社 | ケンタッキーフライドチキン 公式YouTubeチャンネル | 2.24万人 | 33本 | 1,879,364回 | 2013/12/26 |
| くら寿司株式会社 | 178イナバニュース【くら寿司公式】 | 13.4万人 | 641本 | 107,426,311回 | 2019/11/13 |
| 株式会社吉野家 | 吉野家 公式YouTubeチャンネル | 2.11万人 | 23本 | 518,057回 | 2013/04/05 |
| 株式会社王将フードサービス | 餃子の王将 公式チャンネル | 4140人 | 62本 | 806,005回 | 2015/02/04 |
| 株式会社大戸屋ホールディングス | 大戸屋ごはん処【公式チャンネル】 | 1.81万人 | 59本 | 756,327回 | 2016/07/19 |
| 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | セブン‐イレブン・ジャパン 公式チャンネル | 5.98万人 | 41本 | 13,743,135回 | 2016/10/06 |
| 株式会社ファミリーマート | familymart | 3.11万人 | 9本 | 235,662回 | 2006/05/08 |
| 株式会社ローソン | ローソン(LAWSON) | 4.56万人 | 489本 | 13,619,859回 | 2011/11/06 |
(2024年8月30日現在)
飲食店・コンビニ業界のYouTube運用の特徴
大手の飲食チェーンやコンビニでは、テレビCMを中心とした動画により商品の紹介、新商品やキャンペーン情報を発信している傾向がみられました。
今回調査した企業では更新頻度が低いチャンネルが多く、テレビCM投稿以外のYouTubeの活用方法がまだ確立されていないように感じられます。
注目チャンネル:178イナバニュース【くら寿司公式】
2020年1月から投稿を開始し、2024年1月時点で545本以上もの動画を投稿しています。このチャンネルで最も特徴的なのが、社員がYouTuberとして出演している点です。
くら寿司の商品を実食して紹介するだけでなく、料理動画やモーニングルーティンなどYouTuberらしいコンテンツも発信していて、企業チャンネルとしてはユニークな運用方法です。
アパレル・雑貨業界のYouTubeチャンネル活用事例まとめ
アパレル・雑貨業界のYouTubeチャンネル10選
| 企業名 | チャンネル | 登録者数 | 投稿数 | 視聴回数 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ユニクロ | UNIQLO ユニクロ | 10.5万人 | 511本 | 166,815,377回 | 2006/03/18 |
| 株式会社良品計画 | MUJIglobal | 7.44万人 | 441本 | 18,116,839回 | 2009/11/02 |
| 株式会社エービーシー・マート | ABCMART/ABCマート | 1.88万人 | 86本 | 2,336,529回 | 2012/12/04 |
| 株式会社ワコールホールディングス | ワコール Wacoal | 2万人 | 113本 | 6,443,221回 | 2009/02/18 |
| 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド | SamanthaThavasaJP | 1.45万人 | 377本 | 33,237,432回 | 2011/09/28 |
| 株式会社ビームスホールディングス | BEAMSテレビ | 4.36万人 | 1,046本 | 10,082,030回 | 2009/02/17 |
| 株式会社ユナイテッドアローズ | UNITED ARROWS | 1.01人 | 192本 | 3,674,441回2011/06/22 | |
| 株式会社ニトリ | ニトリ公式 NITORI | 10万人 | 401本 | 81,221,798回 | 2011/01/19 |
| 株式会社大塚家具 | インテリアのはなし by IDC OTSUKA | 1.04人 | 305本 | 4,049,908回 | 2020/02/07 |
(2024年8月30日現在)
アパレル・雑貨業界のYouTube運用の特徴
アパレル・雑貨関係の企業では、芸能人やモデルを起用したCM、商品紹介動画が多く投稿されています。
独自のコンセプトを持つ企業が多いので、企業や商品のイメージ、訴求したい強みに合わせてコンテンツを作成しています。チャンネルにその企業の色がはっきり表れており、しっかりとブランディングされているものが多いです。
YouTubeチャンネルのブランディングのコツについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
注目チャンネル:BEAMSテレビ
タレントを起用するのではなく、スタッフが出演してファッションのトレンド情報や自社商品の情報を発信しています。
着回しコーディネートの紹介やファッションチェック、スタッフの趣味やおすすめコンテンツなどについて投稿しています。ユーザーにより近いスタッフが出演することで共感が得られやすく、「スタッフに会うためにお店に行ってみたい」というユーザーを増やすこともできると考えられます。
マスコミ業界のYouTubeチャンネル活用事例まとめ
マスコミ業界のYouTubeチャンネル10選
| 企業名 | チャンネル | 登録者数 | 投稿数 | 視聴回数 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本テレビ | 日テレ公式チャンネル | 100万人 | 2,446本 | 971,133,515回 | 2009/04/28 |
| テレビ東京 | テレビ東京公式 TV TOKYO | 143万人 | 7,738本 | 359,021,661回 | 2005/12/08 |
| 朝日新聞社 | 朝日新聞社 | 53.9万人 | 25,024本 | 751,153,074回 | 2006/08/22 |
| 産経新聞社 | SankeiNews | 56.9万人 | 15,898本 | 513,448,753回 | 2009/10/13 |
| 集英社 | ジャンプチャンネル | 186万人 | 1,724本 | 530,155,625回 | 2018/07/02 |
| 宝島社 | マルチャン / 宝島社マルチメディアチャンネル | 4800人 | 234本 | 1,701,893回 | 2019/06/27 |
| 講談社 | with | 13.8万人 | 1,308本 | 50,870,990回 | 2006/03/24 |
| 東宝株式会社 | 東宝MOVIEチャンネル | 148万人 | 2,579本 | 1,400,649,427回 | 2013/01/18 |
| 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | Sony Music (Japan) | 261万人 | 4,532本 | 3,395,315,306回 | 2011/07/22 |
| 株式会社ウィンズスコア | WindsScore | 26.5万人 | 2,690本 | 325,700,077回 | 2008/09/14 |
(2024年8月30日現在)
マスコミ業界のYouTube運用の特徴
テレビ局は番組予告や放送ドラマのオリジナル版、新聞社はニュースを主に投稿していました。出版社では雑誌ごとにYouTubeチャンネルを開設しているものもみられ、新作の発売情報や付録情報、撮影風景などが多く投稿されています。
特にテレビ・新聞は幅広い年齢層に馴染みの深い媒体であり、10年以上前からYouTubeを活用している企業も多いことから、登録者数・投稿数・視聴回数いずれもどの業界よりも多いことが特徴です。
チャンネル登録者数を増やしたいとお考えの場合は、こちらの記事を参考にしてみてください。
注目チャンネル①with
講談社が発行する女性ファッション誌withのチャンネルでは、女性に需要の高いコスメ・ファッション・ダイエット・料理などに関するお役立ち情報を発信しています。
「元アパレル店員」「美容専門学校講師」「アットコスメ社員」など、各分野に特化したインフルエンサーが情報発信しており、専門性・信頼性の高い動画となっています。
注目チャンネル②WindsScore
吹奏楽の楽譜を制作・出版するウィンズスコアでは、演奏音源をコンテンツとして投稿しています。ユーザーは、概要欄に記載されたURLからオンラインショップへと遷移し、気になった曲の楽譜を簡単に購入することができます。
さらに、購入後もお手本として音源を聴いてもらえるので、チャンネルに多く接触させることでロイヤリティ向上にも繋がっています。
金融・保険業界のYouTubeチャンネル活用事例まとめ
金融・保険業界のYoutubeチャンネル6選
| 企業名 | チャンネル | 登録者数 | 投稿数 | 視聴回数 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMBC日興証券株式会社 | SMBC日興証券株式会社 | 6.75万人 | 269本 | 67,883,754回 | 2013/11/14 |
| 楽天証券 | 楽天証券 | 16.1万人 | 1,178本 | 15,766,672回 | 2009/12/29 |
| みずほ証券 | みずほ証券 公式 | 3.27万人 | 229本 | 800,497回 | 2018/02/14 |
| 三菱UFJ銀行 | 三菱UFJ銀行公式「MUFGBankChannel」 | 1.41万人 | 113本 | 33,270,920回 | 2013/07/05 |
| ソニー損保 | ソニー損保の公式チャンネル | 1.93万人 | 71本 | 198,606,377回 | 2006/10/22 |
| AIG損保 | AIG損保 | 5390人 | 104本 | 1,625,803回 | 2017/02/22 |
(2024年8月30日現在)
金融・保険業界のYouTube運用の特徴
SNSのイメージがあまりない金融・保険業界ですが、専門知識を解説したり、過去のセミナーを配信したり、マーケットの最新情報を発信したりとYouTubeを積極的に活用している企業が多くみられました。
注目チャンネル①SMBC日興証券株式会社
ブランドパートナーであるイチローさんを起用した『おしえて!イチロー先生』シリーズは、2020年6月の公開後から大きな反響を呼び、再生回数384万回(2024年1月時点)となっている動画もあります。
子供から大人まで幅広い年代への企業の認知度を高めるとともに、ブランディングにもつながった事例です。
注目チャンネル②みずほ証券 公式
以前から株価に関する解説動画を投稿していましたが、2020年6月以降はより活発に情報発信されています。
特に「みずほデイリーVIEW」では毎日の最新の情報をいち早く得られるので、ユーザーにとって有益なコンテンツだと言えます。
BtoB企業のYouTubeチャンネル活用事例まとめ
BtoB企業のYouTubeチャンネル10選
| 企業名 | チャンネル | 登録者数 | 投稿数 | 視聴回数 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| StockSun株式会社 | StockSun-WEBコンサルティング- | 4.72万人 | 860本 | 9,815,436回 | 2019/07/11 |
| 株式会社キーエンス | 株式会社キーエンス | 2030人 | 非公開 | 非公開 | 2014/08/20 |
| オムロン株式会社 | オムロン / OMRON | 3750人 | 306本 | 3,158,854回 | 2014/06/06 |
| 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 6640人 | 160本 | 632,888回 | 2006/06/07 |
| 株式会社サイバーエージェント | サイバーエージェント CyberAgent | 4700人 | 144本 | 746,433回 | 2013/11/05 |
| 株式会社DLE | DLE Channel | 22.2万人 | 1,430本 | 156,260,903回 | 2008/04/01 |
| 株式会社セールスフォース・ドットコム | Salesforce Developers Japan | 4110人 | 122本 | 281,341回 | 2014/3/24 |
| freee株式会社 | freee(フリー)【公式】 | 3.98万人 | 344本 | 10,967,654回 | 2013/11/21 |
| Sansan株式会社 | Sansan, Inc. | 5220人 | 94本 | 2,004,866回 | 2011/6/17 |
| サイボウズ株式会社 | サイボウズ Office チャンネル | 2770人 | 82本 | 2,260,979回 | 2013/8/9 |
(2024年8月30日現在)
BtoB企業のYouTube運用の特徴
企業・商品紹介や決算情報、セミナーなどを投稿している企業が多く、中でも製品であれば性能を検証する実験動画、サービス・ツールであれば使い方を解説したり導入事例を紹介したりする動画が多く投稿されていました。
BtoB企業はそもそもYouTubeチャンネルを開設している企業が少なく、開設していても登録者数・投稿数・視聴回数は少ない傾向にあり、YouTubeによるマーケティングがまだあまり活用されていないことが分かります。
YouTubeで成果を出すためには、チャンネル開設初期に方向性を明確に定めておくことが非常に重要です。YouTube運用におけるKPIの設定方法はこちらの記事を参考にしてみてください。
注目チャンネル①:StockSun-WEBコンサルティング-
SEOに強みを持つコンサルティング会社「StockSun」が運営しているチャンネルです。SEOやWeb制作、広告、YouTube動画などマーケティングに関するノウハウやコツを惜しみなく発信しています。専門的な情報を探しているユーザーに見てもらうことができ、SEO企業としての知名度と信頼性を高めることに繋がっています。
StockSun株式会社コーポレートサイト
※こちらのご紹介はStockSun株式会社によるスポンサードコンテンツです。
注目チャンネル②:Salesforce Developers Japan
MAツール『セールスフォース・ドットコム』という企業チャンネルがある一方、こちらの『Salesforce Developers Japan』では過去のセミナーなどを集めて配信しています。
一コンテンツをチャンネルとして独立させているので、ユーザーは求めている情報を探しやすくなります。
その他のYouTubeチャンネル活用事例まとめ
自治体のYouTubeチャンネル2選
| 企業名 | チャンネル | 登録者数 | 投稿数 | 視聴回数 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | いばキラTV – IBAKIRA TV – | 17.3万人 | 6,722本 | 78,526,885回 | 2006/04/16 |
| 岩手県 | 岩手県公式動画チャンネル | 7.12万人 | 2,245本 | 42,785,721回 | 2011/09/20 |
教育業界のチャンネル3選
| 企業名 | チャンネル | 登録者数 | 投稿数 | 視聴回数 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 A.ver | 武田塾チャンネル|参考書のやり方・大学受験情報 | 27.4万人 | 7,785本 | 256,868,902回 | 2008/08/10 |
| 株式会社イーオン | 英会話イーオン公式 | 3210人 | 88本 | 2,608,905回 | 2013/11/13 |
| 株式会社ECC | ECC | 1.85万人 | 257本 | 7,986,750回 | 2014/01/22 |
インフラ業界のチャンネル3選
| 企業名 | チャンネル | 登録者数 | 投稿数 | 視聴回数 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR東日本 | JR東日本公式チャンネル | 8.23万人 | 494本 | 29,248,745回 | 2014/12/16 |
| JAL | japanairlinesjp | 11.8万人 | 874本 | 66,447,536回 | 2012/03/15 |
| ソフトバンク株式会社 | ソフトバンク(SoftBank) | 18万人 | 1,587本 | 64,531,521回 | 2006/04/26 |
製造業のチャンネル3選
| 企業名 | チャンネル | 登録者数 | 投稿数 | 視聴回数 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック株式会社 | Panasonic Japan(パナソニック公式) | 14.4万人 | 2,146本 | 335,195,679回 | 2011/11/10 |
| トヨタ自動車株式会社 | トヨタイムズ | 43.9万人 | 683本 | 128,122,509回 | 2018/12/25 |
| 任天堂株式会社 | Nintendo 公式チャンネル | 304万人 | 3,254本 | 1,685,259,849回 | 2013/03/13 |
(2024年8月30日現在)
まとめ
YouTubeを上手く活用できれば、認知度の向上からブランディング、ファン化まで行うことができます。常にお客様目線に立ち、どのようなコンテンツを発信すれば興味を持ってもらえるかを第一に考えつつ、様々な企業のチャンネルを参考に運用していきましょう。
また、YouTubeマーケティングの成果アップには広告配信も効果的です。以下の記事でYouTube広告の概要を解説していますのでぜひご覧ください。
<関連記事>
YouTube運用についてもっと詳しく学びたい方は、以下の記事もご確認ください!
■企業もYouTubeを活用しよう!YouTube企業アカウントの作り方と運用のコツ
■YouTube運用のKPI設定ガイド!最適な目標に向かって運用するために
■YouTubeチャンネルをブランディングするための5つのステップと成功事例
■企業がYouTubeチャンネル登録者数を増やすために確認すべき7つのこと
YouTubeコンサルティングサービスのご紹介┃株式会社フルスピード
当オウンドメディアGrowthSeedを運営しております株式会社フルスピードでは、YouTubeチャンネルコンサルティング・広告運用代行サービスを承っております。当記事にて「YouTubeの可能性を感じたものの社内リソースが不足していてアクション出来ない」とお悩みにのお客様や、「YouTubeチャンネルの運用ノウハウが不足しており挑戦しづらい」とお悩みのお客様は、株式会社フルスピードのYouTubeコンサルティングサービスをぜひご検討ください。YouTubeチャンネルコンサルティングサービスの詳細資料は下記バナーから無料でダウンロードいただけます。ぜひ、ご確認くださいませ。
松崎 明日香
マーケティング部
2020年に新卒入社後、オウンドメディア『GrowthSeed』の運営/ライティングを中心に、メルマガ運用、広告運用など自社のマーケティング業務に幅広く携わる。お問い合わせ数・売上アップを目標に日々奮闘中。趣味は喫茶店・カレー屋巡り。

-

【2025年最新】SNSの利用者数とユーザー属性や特徴まとめ
- SNSマーケティング
-

【図解】Facebook広告の出し方を分かりやすく解説(2025年最新)
- SNS広告
-
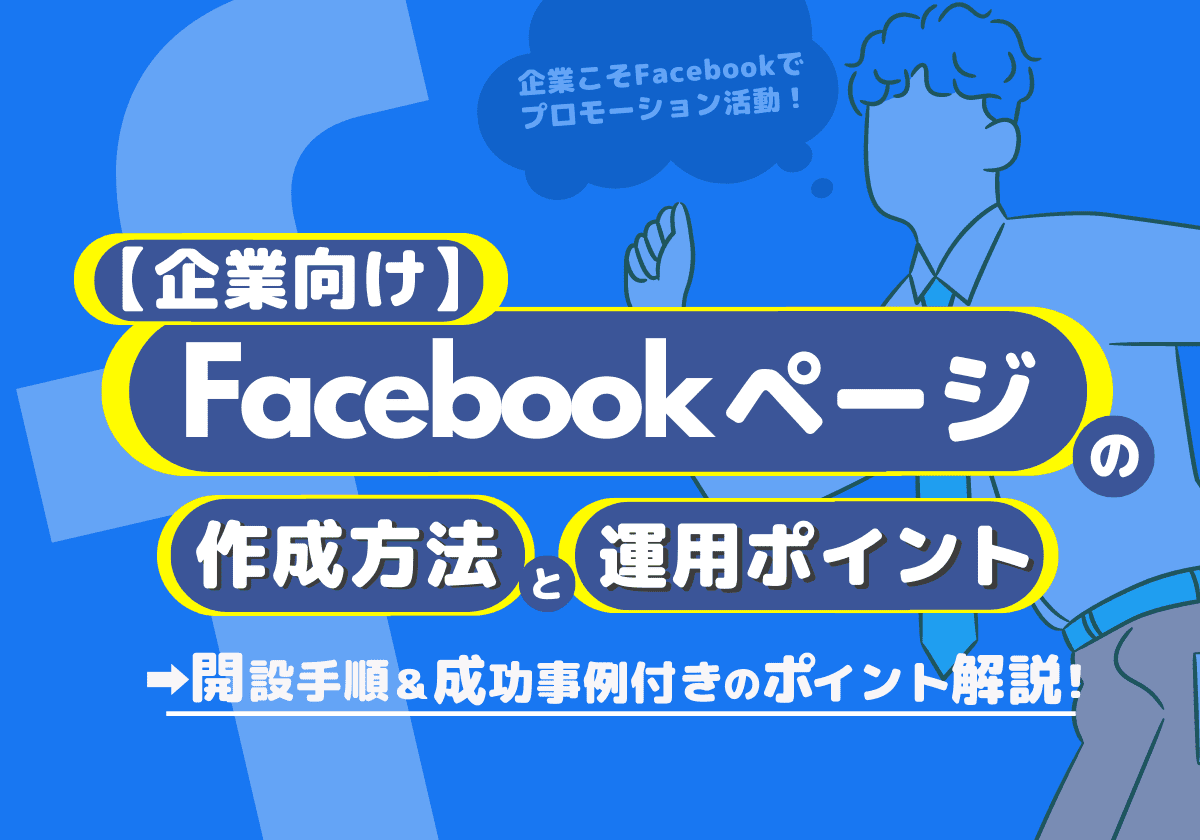
Facebookページの作成方法と運用方法のコツを解説!(企業向け)
- SNSマーケティング
- SNS運用
-
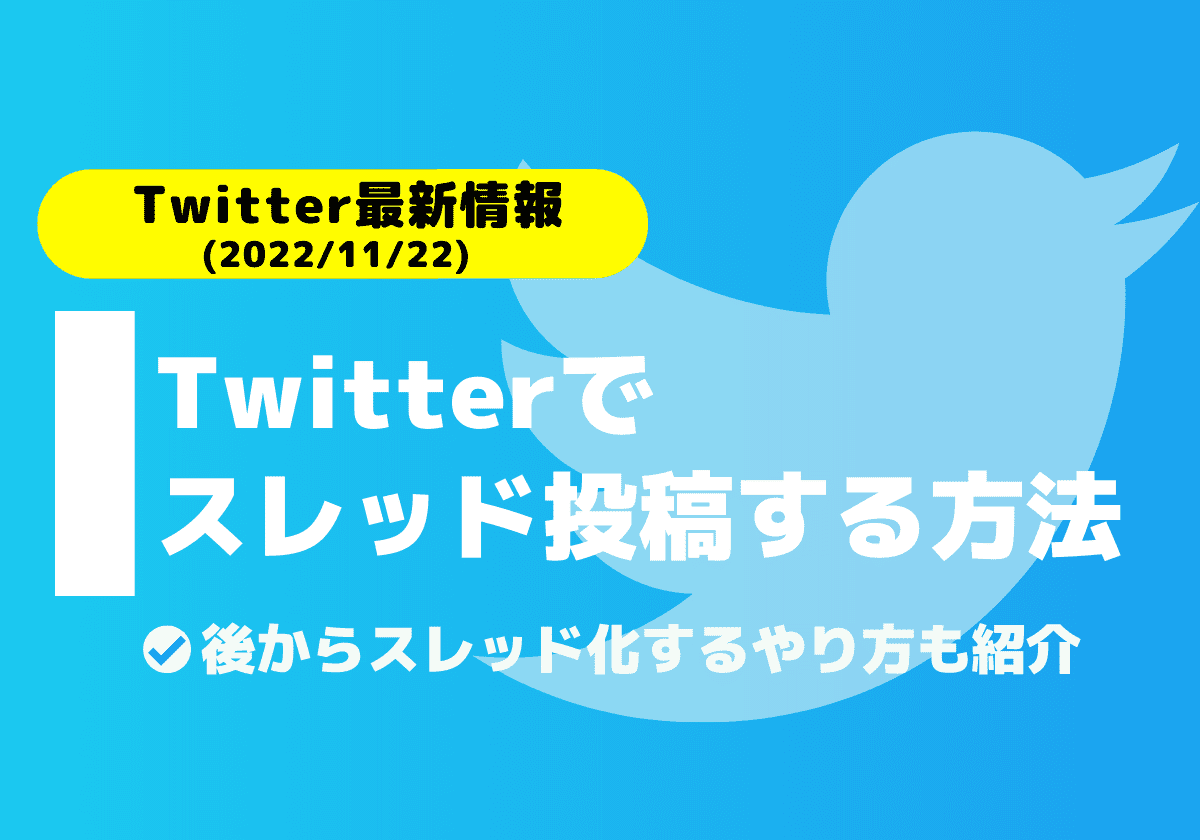
X(Twitter)のスレッドとは何か?リプライとの違いやスレッド投稿のやり方を紹介!
- SNS運用
- 最新ニュース
-

SNS投稿に最適な画像サイズ一覧まとめ【X(Twitter)・Facebook・Instagram・LINE】
- LINE
- SNSマーケティング
- SNS運用
-
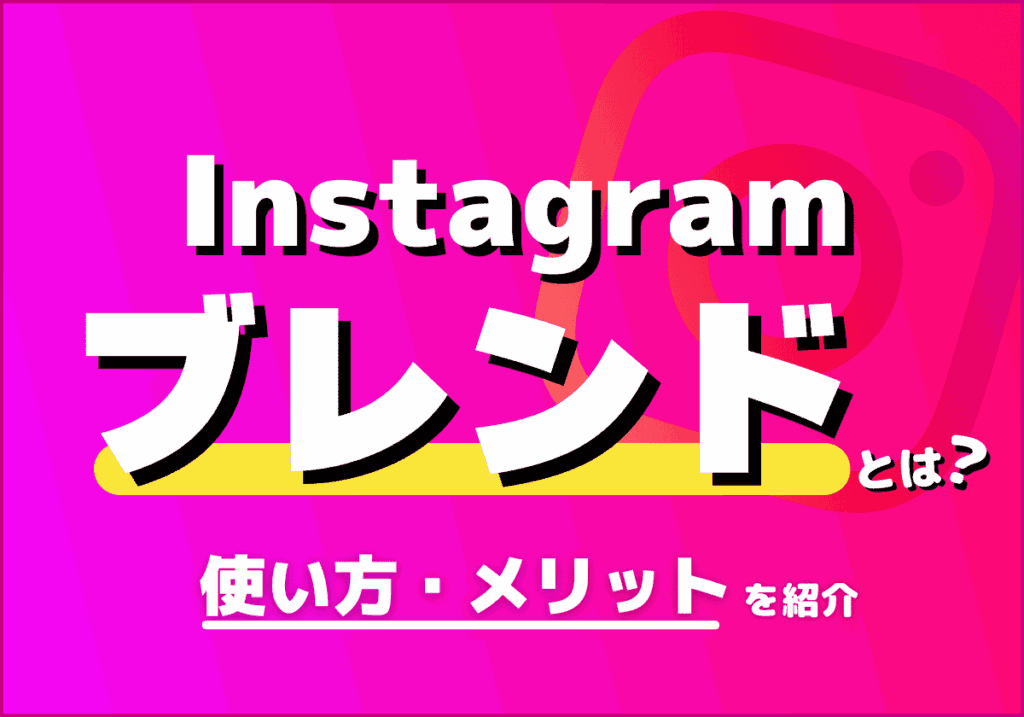
Instagramのブレンドとは?使い方・メリットまとめ
- 最新ニュース
-
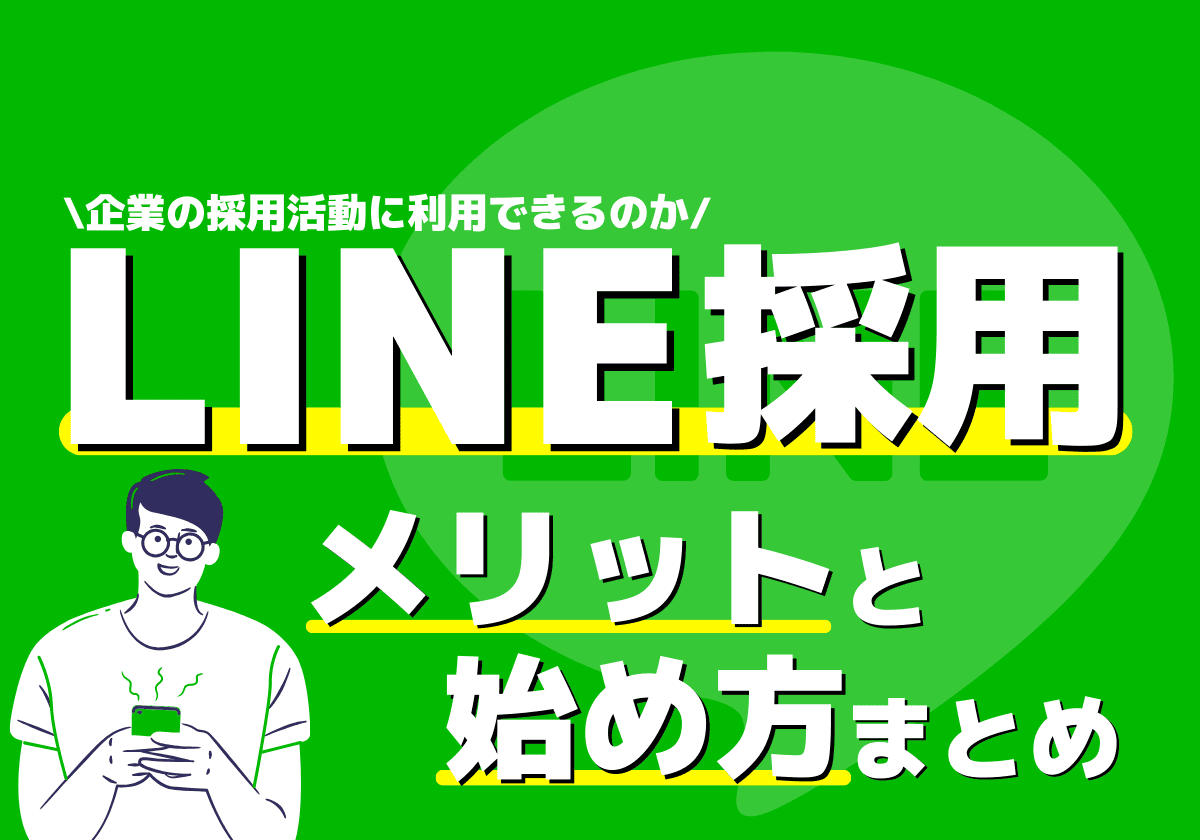
LINEは採用活動に利用できるか?メリット・始め方まとめ!
- LINE
-
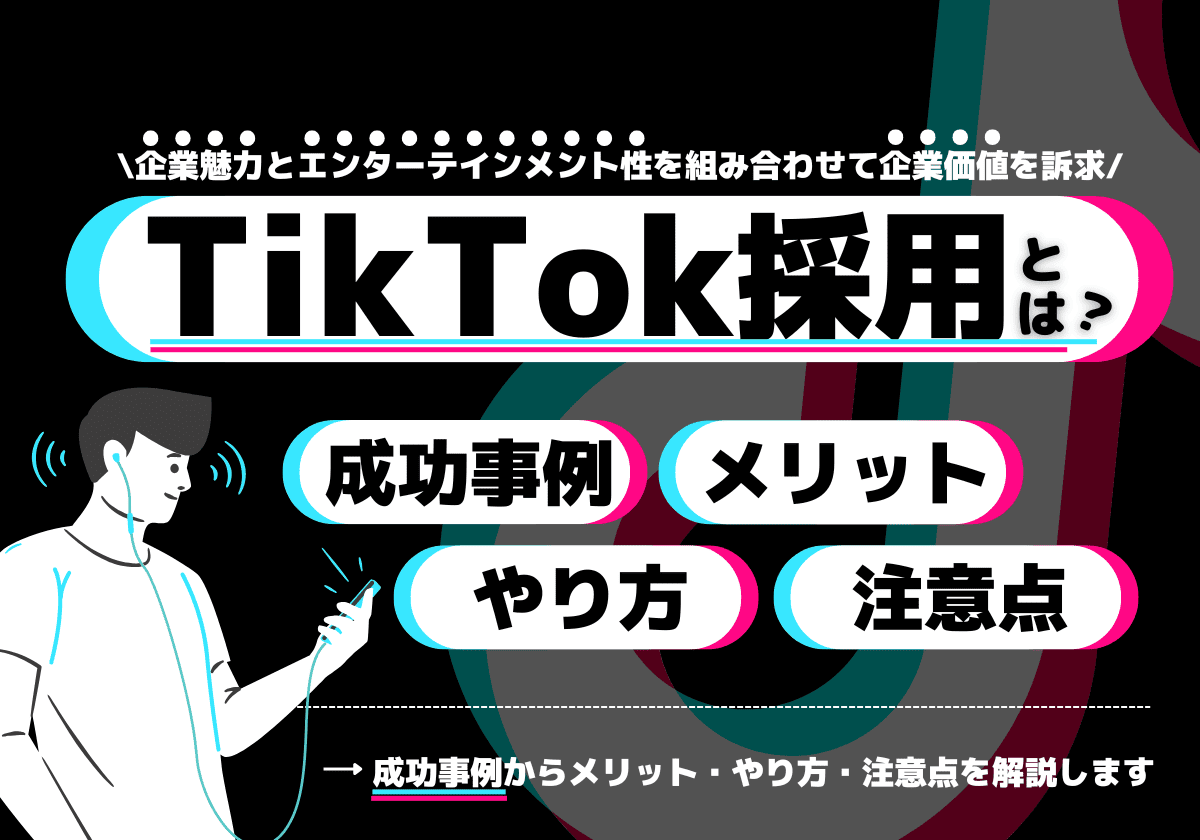
TikTok採用とは?成功事例・メリット・デメリット・やり方・注意点まとめ
- TikTok
-
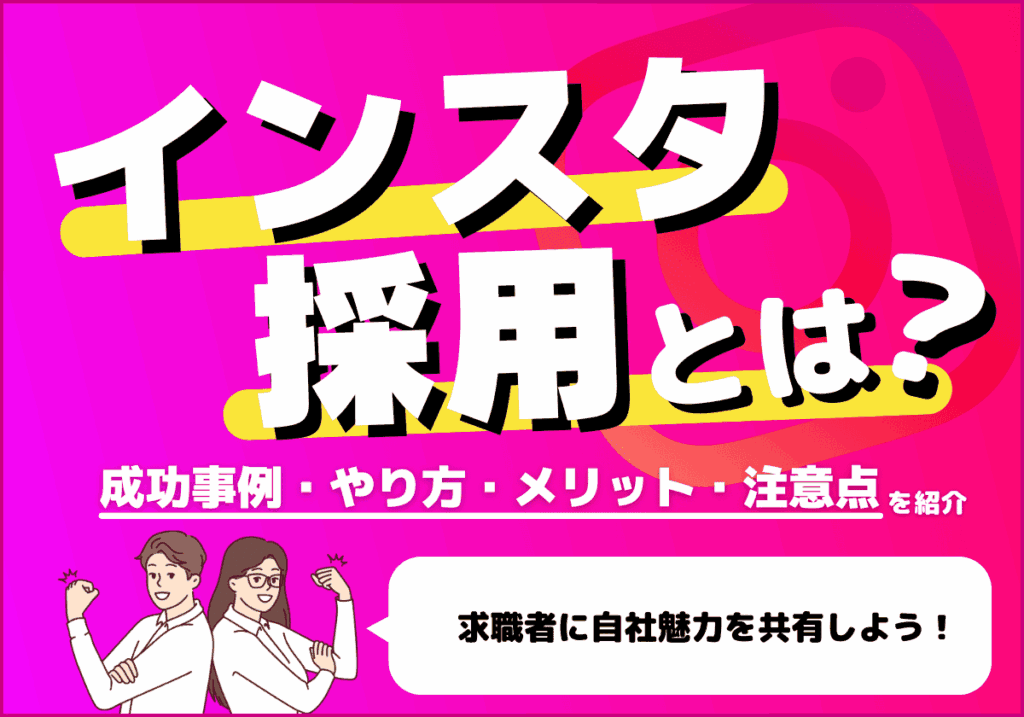
Instagram採用とは?成功事例・やり方・メリット・注意点まとめ!
-
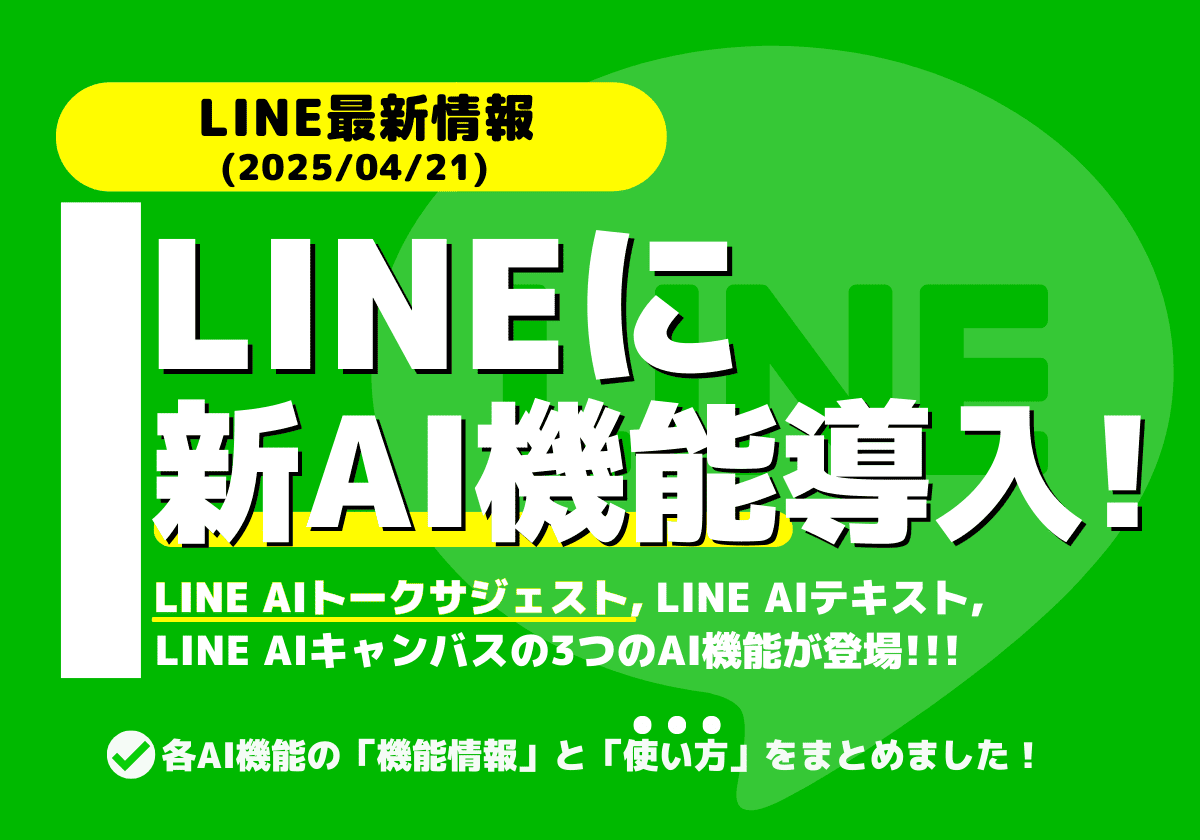
LINE AIトークサジェストで返信しよう!使い方・おすすめ利用タイミング・関連AI機能まとめ!
- LINE
- 最新ニュース