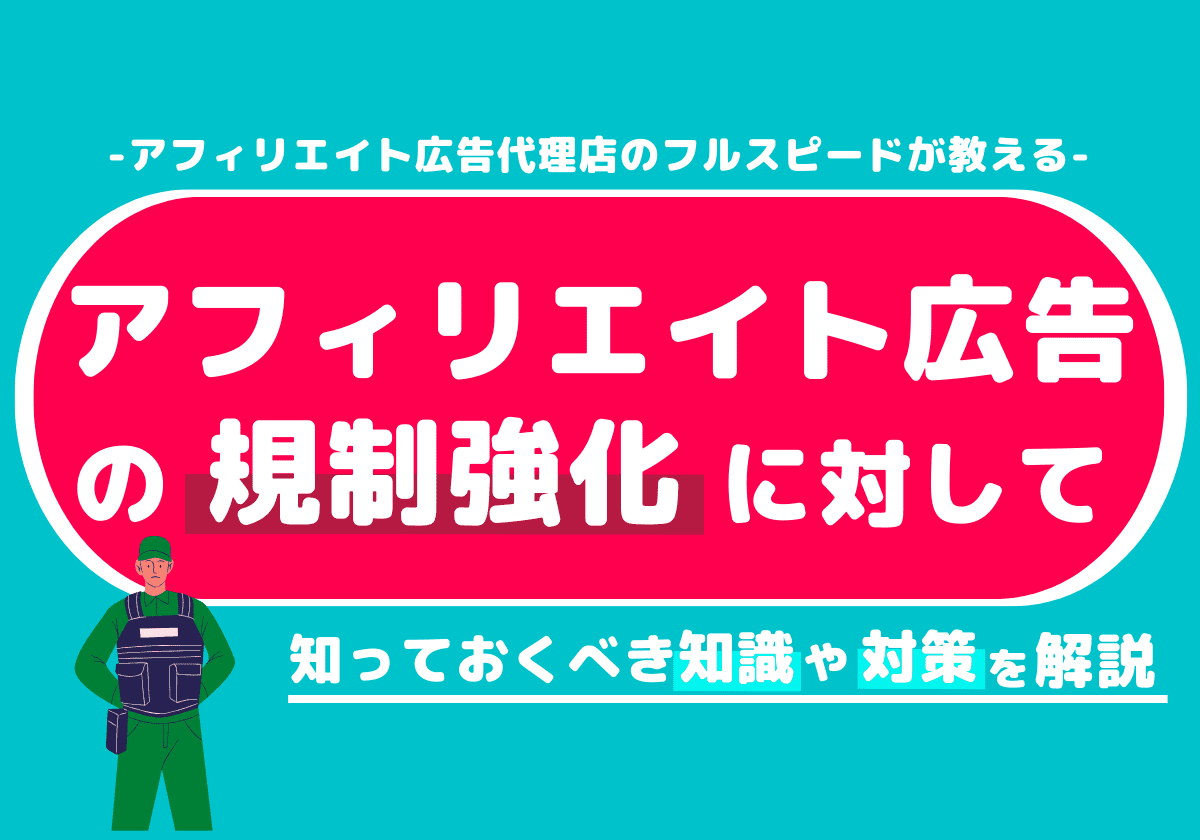アフィリエイト広告の規制強化に対して知っておくべき知識や対策を解説
知らなきゃマズイ!インターネット関連の法律
公開日:2015年12月17日
最終更新日:2025年01月09日

こんにちは。Growth Seed編集部です。
WEBサイトを運用する場合に知っておかなければいけないインターネット関連の法律は多くあります。「知らなかった!」では済まされず、結果的に大きな損失を招く可能性もあります。そうならないために、「インターネットの法律」を7つご紹介します。
今回は「サイト運営全般に関わる法律」と「サイトのジャンルや特性による法律」の2つに分類、代表的な法律に絞り、初心者にも分かりやすいように解説します。
↓【無料DL】「SEO内部対策チェックシート」を無料ダウンロードする
目次
全てのWEB担当者は理解しよう!サイト運営全般に関わる法律
まずは、サイト運用に関わるものは必ず知っておかなくてはいけないインターネット全般の法律を3つご紹介します。
01.個人情報保護法
名前のごとく個人の情報を守るために2005年4月に施行された法律です。
インターネットから申し込みをしたり、購入する機会が増えたことで、情報のデータベース化が進んでいます。最近は、ちょっとした気の緩みからの個人情報漏えいの事件や事故が相次いでおり、社会的信用を損なうニュースを多く見かけます。
漏えいに歯止めをかけるためにも、正しく理解し、正しく扱いましょう。
個人情報とは?
・生存する個人に関する情報
・特定の個人を識別することができるもの
・他の情報と容易に照合することができもの
に分類され、「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。
とガイドラインの定義(法第2条関連)に記されています。
義務の対象は?
個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6カ月以内のいずれの日においても5,000を超える事業の用に供している者は、「個人情報取扱事業者」に該当します。
個人情報取扱事業者の義務は?
・個人情報の利用目的関係
・個人情報の取得関係
・データ内容の正確性の確保
・安全管理措置
・従業者や委託先の監督
・第三者への提供
・保有個人データに関する事項の公表等
・保有個人データの開示・訂正・利用停止等
・理由の説明
・開示等の求めに応じる手続
・手数料
・苦情の処理
などを定め、社内体制の整備をする必要があります。
所轄官庁は?
平成21年9月1日に内閣府から消費者庁に移管しました。
詳しくは消費者庁のページをご覧ください。(記事の引用元)
02.迷惑メール防止法
2002年に施行され2008年12月1日に改正、営業・販促目的のメールは、原則としてあらかじめ同意した者に対してのみ送信が認められる「オプトイン方式」が義務付けられました。
営業や宣伝目的にメール配信をしたい事業者は、ユーザーから会員登録時や商品購入時などに何らかの形で事前に同意を得る必要があります。
メールを送信する際の義務は?
・送信に同意した者から、広告宣伝メールの受信を拒否する旨の通知を受けた場合は、以後の送信をすることはできません。
・広告宣伝メールを送信する場合は、送信者の氏名・名称や、受信を拒否する場合の通知先など、一定の事項を表示しなければなりません。
・広告宣伝メールの送信をする場合は、同意があったことを証する記録を保存しなければなりません。
対象となる電子メールは?
・法律改正により、広告宣伝メール全般について、オプトイン方式や、特定の事項の表示が義務づけられることとなりました。
・SMS(携帯電話どうしで短い文字メッセージを電話番号により送受信するサービス)も対象となります。
・他人の営業のために送信されるものも対象となります。
・非営利団体や営業を営まない個人が送信する電子メールは対象外です。
・海外から送信され、日本で着信する広告宣伝メールも対象となります。
違反した場合の罰則は?
・罰則が強化され、法人に対する罰金額が100万円以下から3000万円以下に引き上げられました。
・広告宣伝メールの送信を委託した者や、電子メール広告業務を受託した者が、行政による命令の対象に含まれるなど、法律の規律対象が拡大されました。
・総務大臣が、プロバイダなどに対し、迷惑メールの送信元アドレスなどについて契約者情報の提供を求めることが可能となりました。
・海外から発信される迷惑メールに対応するため、迷惑メール対策を行う外国の執行当局に対し、迷惑メール送信者に関する情報などを提供することが可能となりました。
違反した業者は、総務省のサイトで「特定電子メール法違反に係る措置命令の実施」として会社概要が開示されてしまいます。
所轄官庁は?
詳しくは総務省のページをご覧ください。(記事の引用元)
03.景品表示法
実際よりも良く見せかける表示が行われたり、過大な景品類の提供が行われたり、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品・サービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
このような不当表示や不当景品から消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」です。
簡単に言うと、うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止する法律です。
不当表示とは?
不当表示には大きく分けて3つの種類があります。
・優良誤認表示
商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。
例えばこのような表示はNG
a.牛肉のブランドを偽って表示、良くあるのが有名ブランドであるかのように表示するケース
b.実際には10万km走行した中古車であるにもかかわらず、「走行距離3万km」と少なく表示するケース
c.適正な比較をしていないのに「○○実績No.1」を誇大に表示するケース
など
・有利誤認表示
価格を著しく安くみせかけるなど、取引条件を著しく有利にみせかける表示は、有利誤認表示として禁止しています。
例えばこのような表示はNG
a.携帯電話通信の料金の場合。実際には、自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較であるにもかかわらず、あたかも「 自社が最も安い 」かのように表示。
b.商品の内容量の場合。実際には、他社と同程度の内容量しかないにもかかわらず、あたかも「 他社商品の2倍の内容量 」であるかのように表示。
c.家電量販店の販売価格の場合。店頭価格について、競合店の平均価格から値引きすると表示しながら、その平均価格を実際の平均価格よりも高い価格に設定し 、そこから値引きするケース。
・その他、誤認されるおそれのある表示
優良誤認表示及び有利誤認表示以外にも、景品表示法に基づいて、6つの告示が定められています。
a.無果汁の清涼飲料水等についての表示
b.商品の原産国に関する不当な表示
c.消費者信用の融資費用に関する不当な表示
d.不動産のおとり広告に関する表示
e.おとり広告に関する表示
f.有料老人ホームに関する不当な表示
違反行為には措置命令が行われますが、平成26年11月には景品表示法が改正され徴金制度も導入されました。
所轄官庁は?
詳しくは消費者庁のページをご覧ください。(記事の引用元)
知ってて損はない!サイトジャンルに関わる法律
次に、サイトのジャンルや特性ごとに定められている法律を4つご紹介します。
01.特定商取引法(別名:特商法)
訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めた法律です。
対象になる取引の形態は、「1.訪問販売」「2.通信販売」「3.電話勧誘販売」「4.連鎖販売取引」「5.特定継続的役務提供」「6.業務提供誘引販売取引」「7.訪問購入」の7つがあります。
ネットショップなど、インターネット上で商品を販売するECサイトは「2.通信販売」に該当し、「特定商取引法に基づく表示」のページを用意し消費者へ特定情報を開示しなければなりません。
表記方法は?
独立した「特定商取引法に基づく表示」ページを作成し、各ページから閲覧できるように分かりやすい場所に内部リンクを設置します。
表記項目は?
表示する事項は「広告の表示(法第11条)」により次のように定められています。
1.販売価格(送料についても表示が必要)
2.代金の支払い時期と方法
3.商品の引渡時期
4.商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)
5.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
7.申込みの有効期限があるときには、その期限
8.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
9.商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
10.いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
11.商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
12.請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額。
13.電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
全ての項目が必要かというと必ずしもそうではなく、当該事業に関わる項目を適切にピックアップして掲載すれば問題はありません。といっても悩むケースがあると思います。
例えば、個人事業主の方であれば「電話番号は固定番号じゃなければいけないのか?」など。
経済産業局へ問合わせしたところ「確実に連絡が取れれば固定電話に限らず携帯番号やIP番号でも問題ない」とのことでした。ただ、運用や表記上は問題ありませんが、一般消費者からすると不安に思うかもしれない為、信頼性の観点から検討は必要でしょう。
細かい点で疑問に思うのが法律、悩んだ時は所轄官庁の経済産業局へ問合わせしてみましょう。親切に教えてくれます。
所轄官庁は?
詳しくは経済産業省のページをご覧ください。(記事の引用元)
02.古物営業法
古物の取引には盗品などが紛れ込む可能性があることから、許可制度を導入しています。WEBサイトに関わることに限定された法律ではなく、中古品を買い取って販売する物においては必ず「古物商許可証」を取得しなければなりません。
古物ビジネスを行うため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物とは?
・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
をいい、細かくは13種に分類されています。
「美術品類」「衣類」「時計・宝飾品類」「自動車」「自動二輪・原付」「自転車類」「写真機類」「事務機器類」「機会工具類」「道具類」「皮革・ゴム製品類」「書籍」「金券類」
届け出が必要なシチュエーションは?
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理等して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
などの業務を行っている場合は古物商許可が必要です。
WEBサイトにかかわる身近な例で言うと以下のようなサイトです。
・中古の本やCDを買い取って販売しているサイト
・中古の衣料品やブランド品を買い取って販売しているサイト
・中古の家電を買い取って修理して販売しているサイト
申請する場合は?
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
私も個人で取得したことがあるのですが提出書類が非常に多くあります。例えば「略歴書」といいながら履歴書を提出したり、「登記事項証明書」「土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)」をとるのに法務局を行ったり来たりしたり、そういえば営業所の平面図も書かされました。思った以上に必要書類が多く手間のかかる申請です。
許可を取った後は?
サイトで古物取引を行う場合は、サイト上の分かりやすい場所、フッターなどに「許可番号」「許可した公安委員会名」を表記しなければなりません。
そして、サイトURLを公安委員会に届けます。届け出をすると公安委員会が管理する古物商届出業者一覧に掲載されます。
例えば、神奈川県でWEBサイトを利用して古物取引を行う古物商一覧をみたい場合は、以下のデータベースにアクセスしてみましょう。
神奈川県公安委員会/古物商届出業者一覧
所轄官庁は?
都道府県公安委員会
詳しくは警視庁のページをご覧ください。(記事の引用元)
03.探偵業法
悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶たなかったことから、平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」といいます。)」が制定され、営業を開始しようとする日の前日までに営業所ごとに届出をし、探偵業届出証明書の交付が義務付けされました。
探偵業務とは?
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報を当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する。
(探偵業の業務の適正化に関する法律の(定義)第二条より)
便利屋等と称しても、探偵業務と同様な業務を行う業者も届出が必要です。
申請する場合は?
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
許可を取った後は?
サイト上の分かりやすい場所に「探偵業届出証明書番号」「許可した公安委員会名」を表記しなければなりません。
所轄官庁は?
都道府県公安委員会
詳しくは警視庁のページをご覧ください。(記事の引用元)
04.インターネット異性紹介事業
インターネット異性紹介事業は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号において定義されています。(ガイドラインより引用)
インターネット異性紹介事業とは?
01.面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
02.異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
03.インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
04.有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
以上の4要件をすべて満たす事業をいいます。
申請する場合は?
営業所の所在地を管轄する警察署の保安係が窓口です。
許可を取った後は?
サイト上の分かりやすい場所に「認定番号」「インターネット異性紹介事業届出済み」を表記しなければなりません。
所轄官庁は?
都道府県公安委員会
詳しくは警視庁のページをご覧ください。(記事の引用元)
まとめ
いかがでしたでしょうか。
法律は聞きなれない用語も多く戸惑うこともあると思います。でも、いざという時にスルーしてしまい信頼の低下につながっては元も子もありません。「あれ?これってあの法律に抵触するのでは?」と疑問に思うだけでも防止策につながります。
伝えたいことは二つ。
01.守るべき法律をしっかり理解してサイト運用に役立てましょう。
02.サイトを見る時の信頼性を判断するヒントにしましょう。
※全て2015年11月末時点の情報です。
それでは次回、またお付き合いください!ありがとうございました!
株式会社フルスピードのSEO関連サービスのご紹介
-

コンテンツSEO多様な業態・WEBサイトで100,000記事以上の幅広い制作実績があります。 -

記事制作代行
コンテンツ制作コラムや導入事例、アンケート記事、専門家監修記事の制作を代行するサービスです。 -

法人向けSEO研修企業のマーケティング担当者が第一線のプロからSEOを学べるリスキリングサービスです。
株式会社フルスピードは世界で60万人が導入する最高水準のSEO分析ツールAhrefsのオフィシャルパートナーでもあり、これまで培ってきたSEOノウハウとAhrefsのサイト分析力を活かしたSEOコンサルティングサービスをご提供することが可能です。SEOコンサルティングサービスの詳細に関しましては上記バナーをクリックしてご確認くださいませ。お気軽にご相談ください。

-
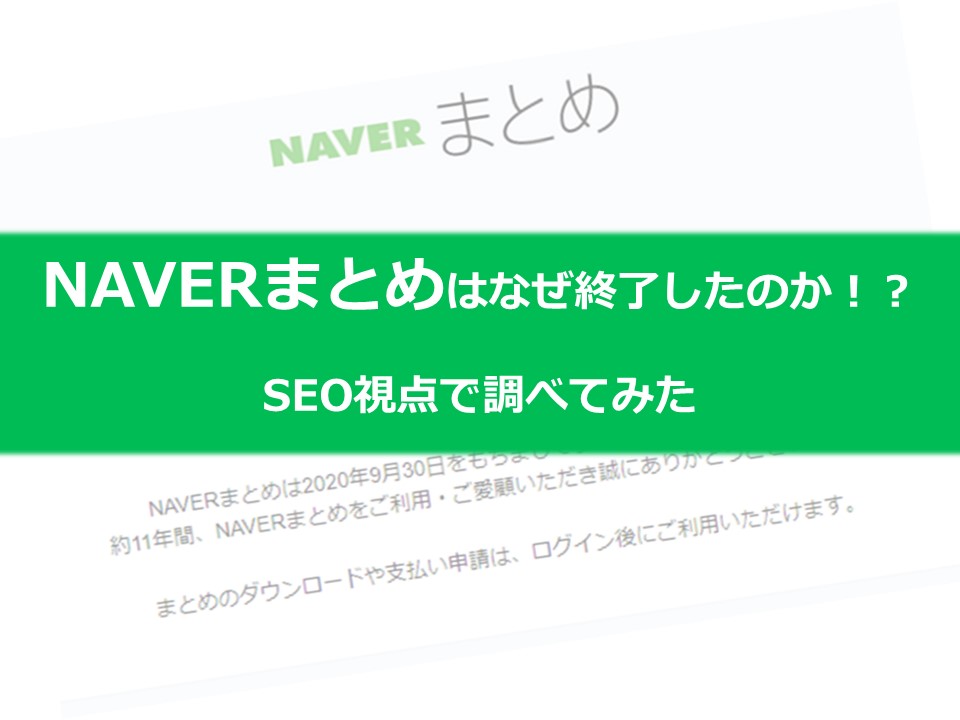
なぜNAVERまとめはサービス終了したのか!?SEO視点で調べてみた
- Ahrefs
-
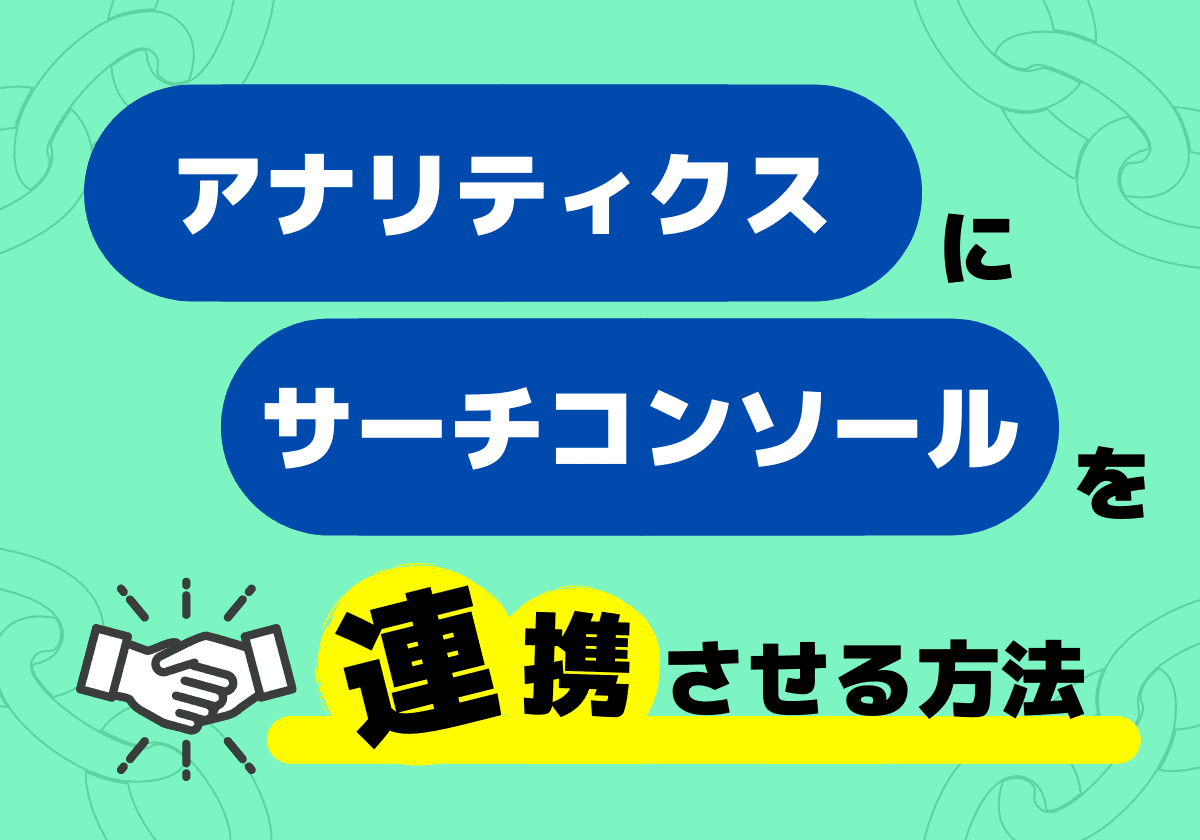
GA4とサーチコンソールの連携方法!メリット・確認方法・連携できない時の対処法まとめ
- Google Search Console
- Googleアナリティクス
-
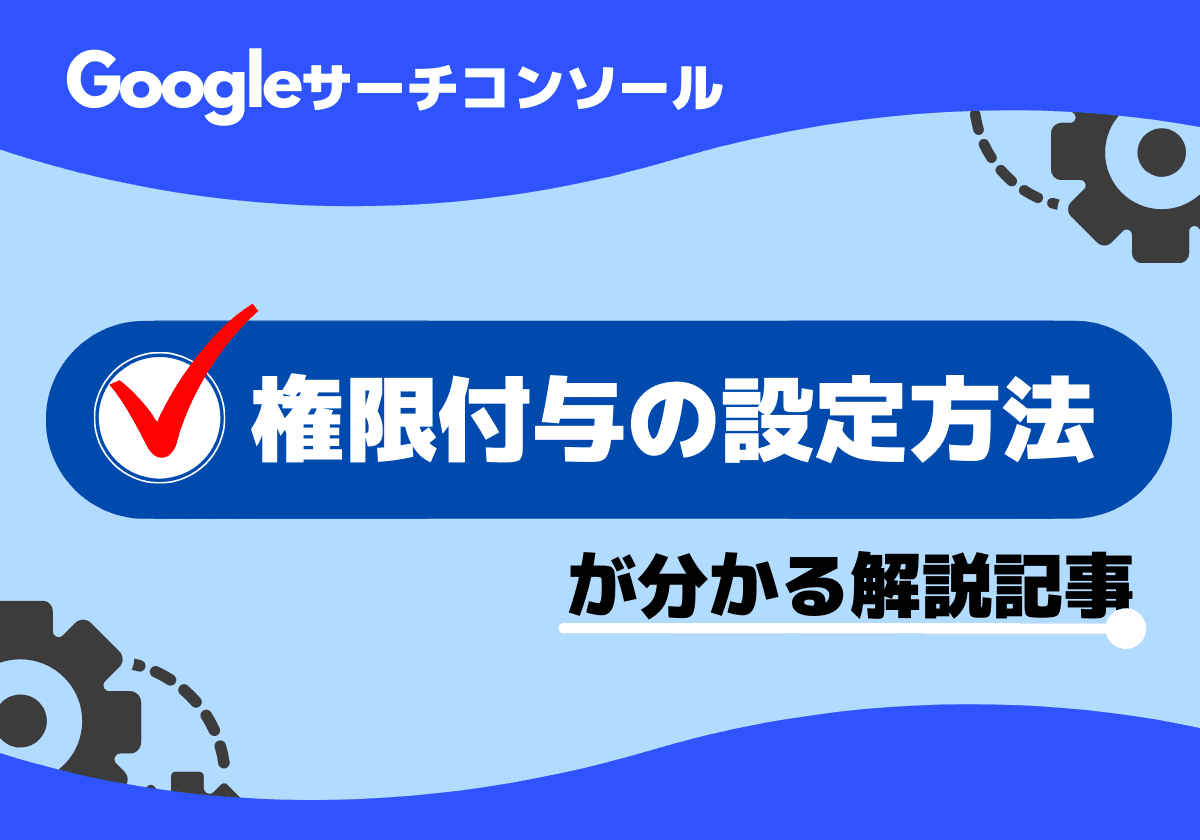
サーチコンソールの権限付与の方法を画像解説┃2025年最新
- Google Search Console
-
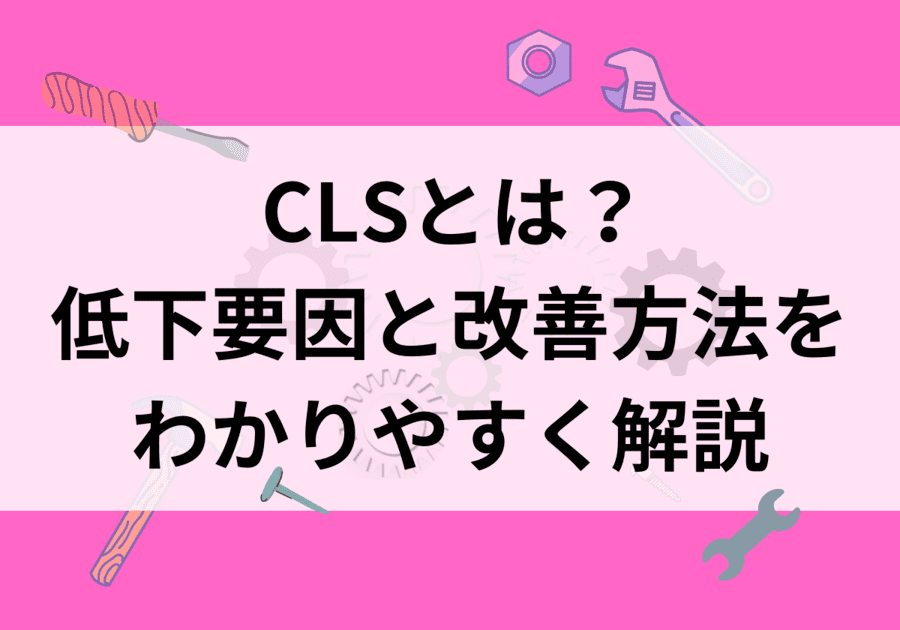
CLSとは? 低下要因と改善方法をわかりやすく解説
- Google検索アルゴリズム
- SEO内部対策
- SEO基礎
-
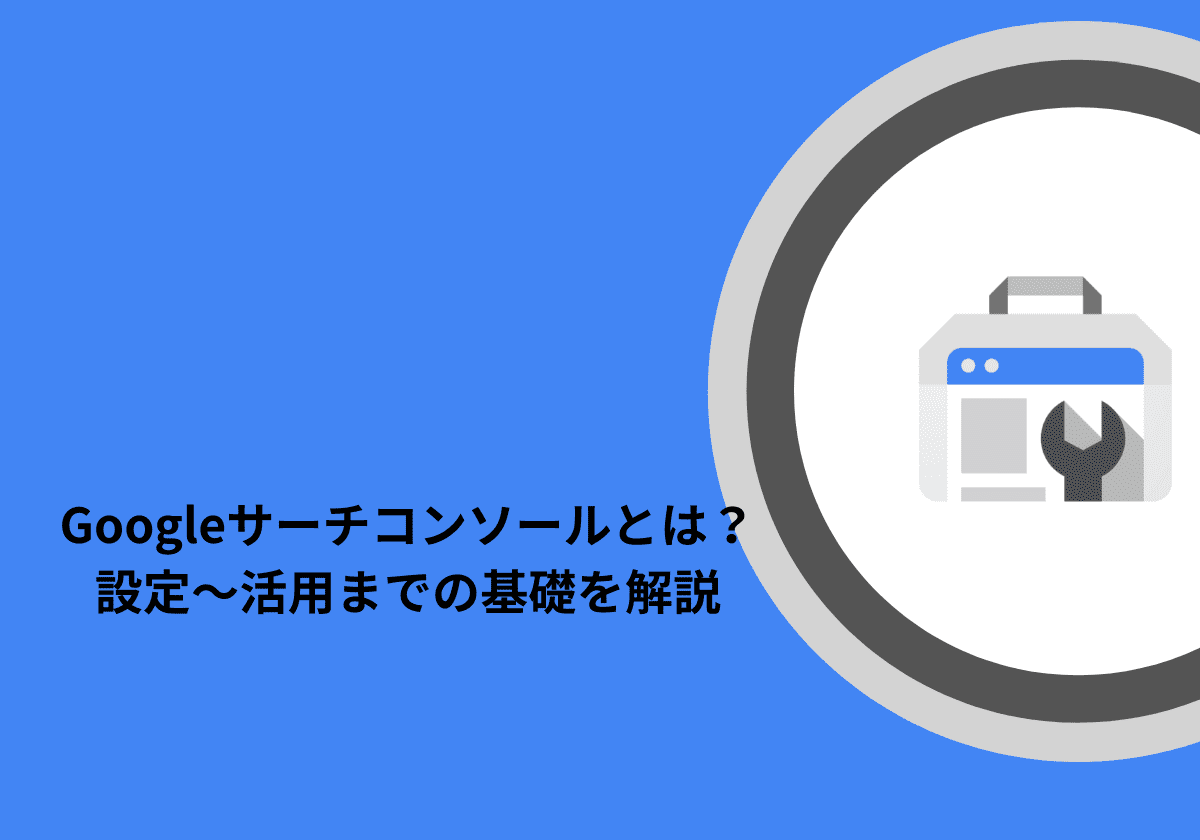
Googleサーチコンソールとは?設定~活用までの基礎を解説【2025年最新版】
- Google Search Console
- SEO 分析
-
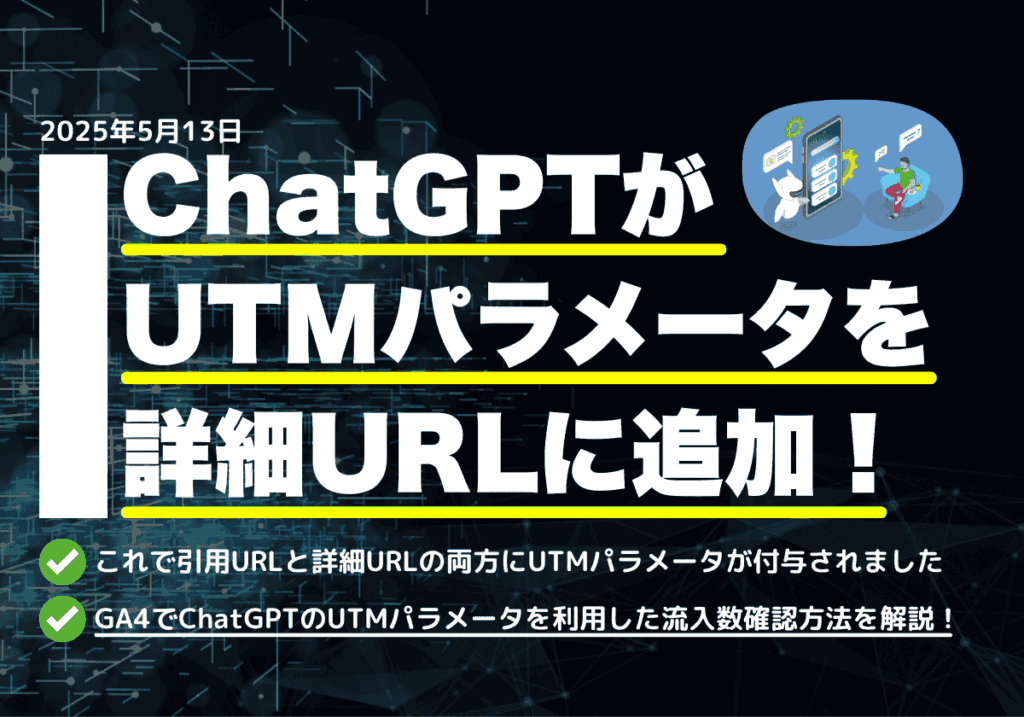
ChatGPTがUTMパラメータを詳細URLに追加するアップデート実施!GA4でChatGPTからの流入数を確認する方法も解説!
- 最新ニュース
-

Google検索結果を音声データで聞く機能(Audio Overviews)がSearch Labsに登場!
- 最新ニュース
-
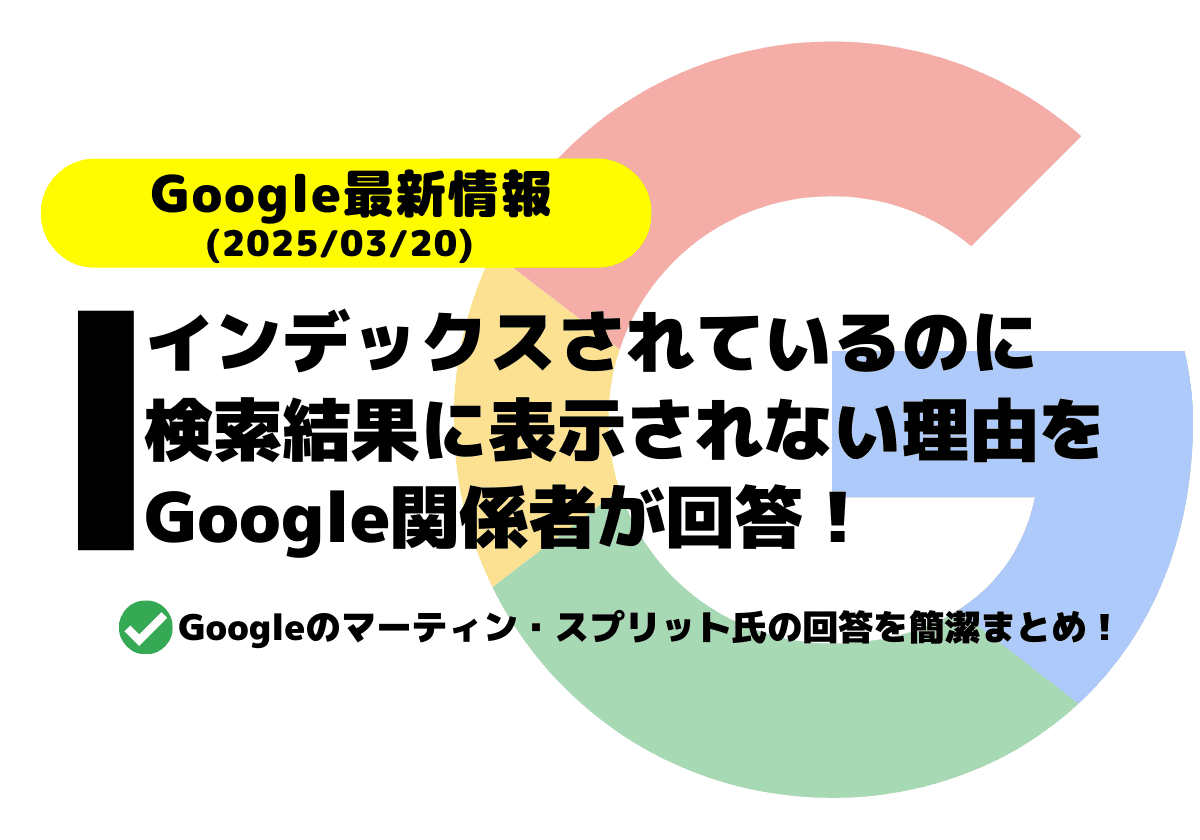
「インデックスされているのに検索結果に表示されない理由」をGoogle関係者が回答!
- Google検索結果
- 最新ニュース
-
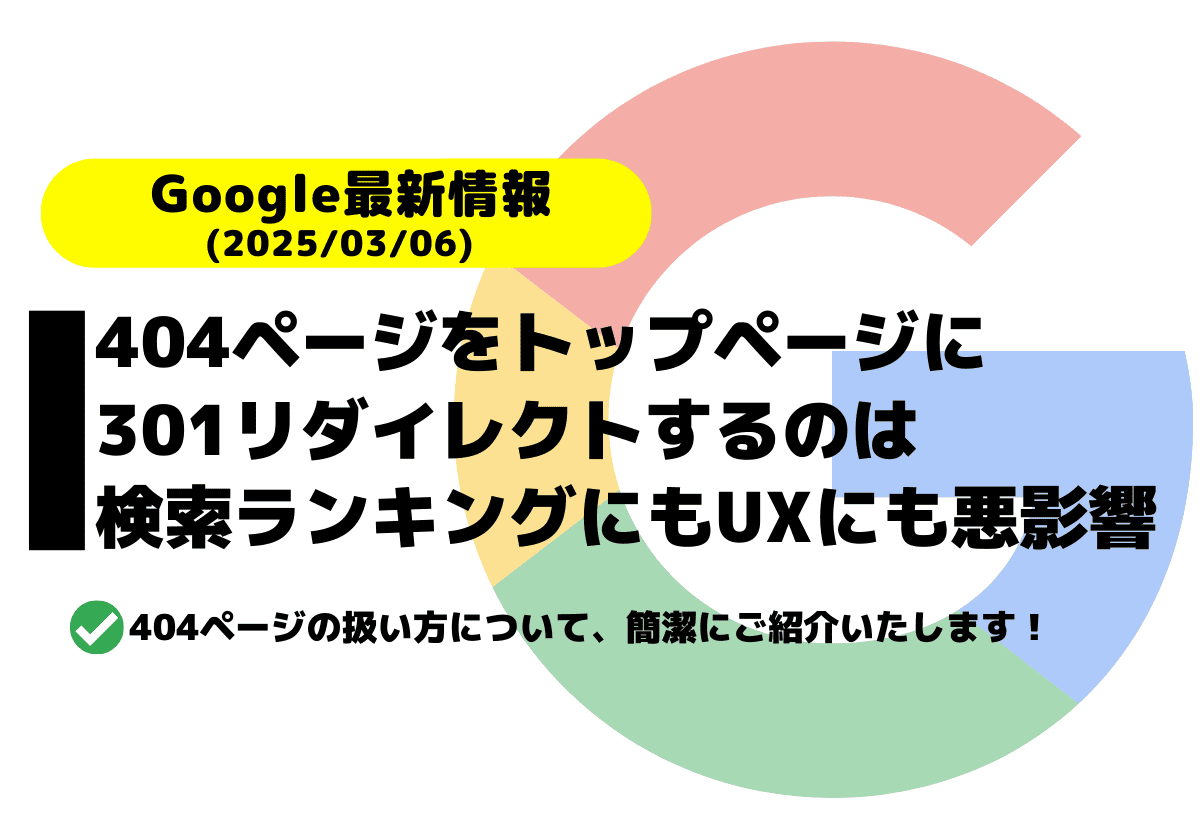
404ページをトップページに301リダイレクトするのは検索ランキングにもUXにも悪影響
- Google検索結果
- 最新ニュース
-
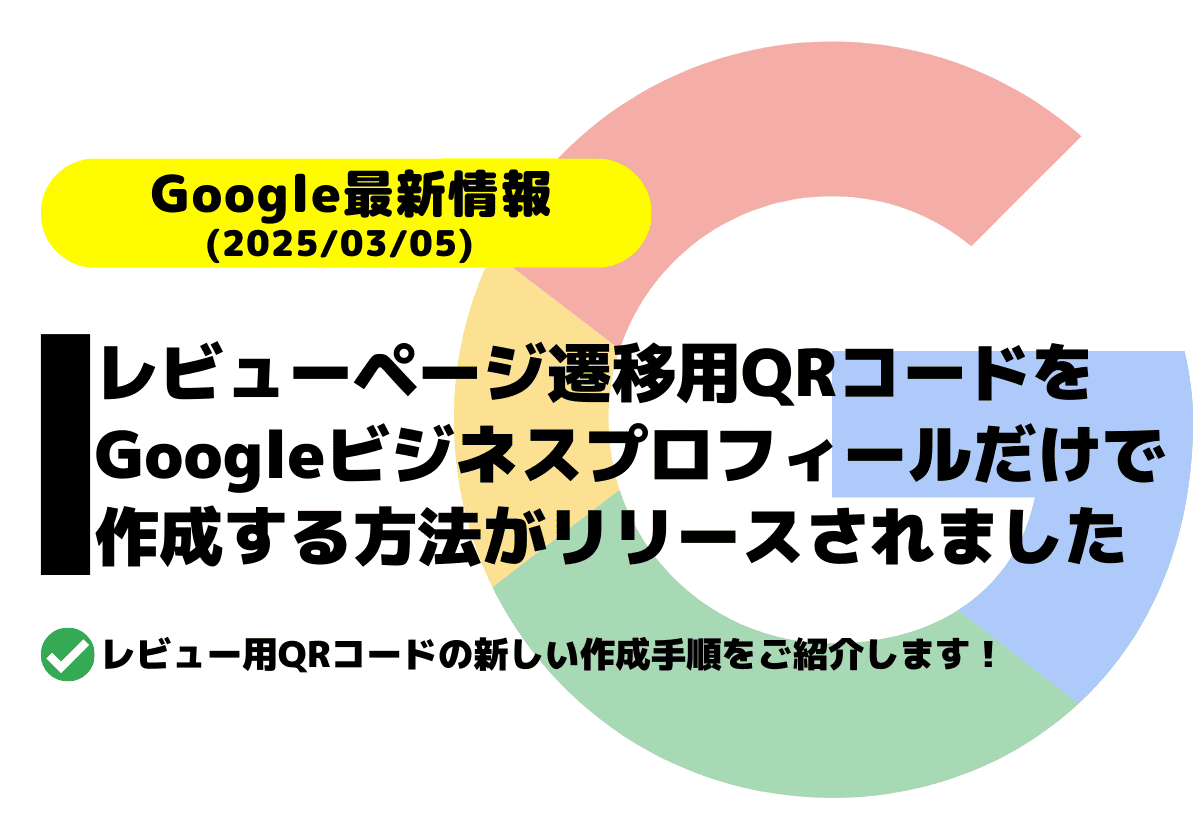
「レビュー用QRコード」がGoogleビジネスプロフィールだけで作成可能に!作り方まとめ!(外部サイトを利用せず作る)
- 最新ニュース